海外移住、海外赴任が決まると困るのがお金周りの整理事可と思います。銀行口座はどうするの?証券口座はどうするの?という疑問がふつふつと浮かびあがると思いますが、今回ご紹介するiDeCoも
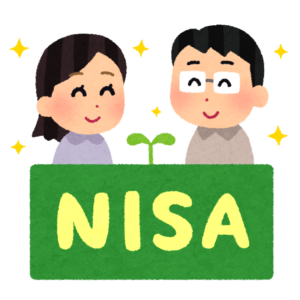
iDeCoってなに???
iDeCoとは老後資産作りのために、国民年金や厚生年金に上乗せして、自分で掛金を運用して資産を運用させることができる制度です。
- 掛金は全額所得控除
- 運用益が非課税
- 60歳以降の受取時に控除あり
上記の税制メリットを活用して老後の資金確保をします。
2022年10月からは企業型のiDeCo加入要件が緩和されたことで、企業型DCに加入している会社員もiDeCo加入可能になり、iDeCo加入対象者が増加しました。
2024年12月からは
- 企業型DCとDB(確定給付企業年金)の拠出限度額の変更
- iDeCoの拠出可能額の変更
も控えており、さらなる盛り上がりを見せております。
海外在住・赴任者でも条件を満たせばiDeCoでの資産運用が可能!
2022年5・10月に施行された法改正により海外に居住する方でもiDeCoの利用が認められるようになりました。
- 日本国内の会社に勤めながら、海外駐在・海外赴任の場合→厚生年金被保険者
- 日本国籍を有する国民年金の任意加入被保険者(20歳以上65歳未満)
上記2つの条件のどちらかを満たすことでiDeCoは可能となります。
つまり、1の場合は、一般的な駐在員は特に気にせずiDeCoは可能と考えてください。
2の場合は、企業に勤めていなくても、日本人であり、国民年金に加入して納めていれば例え海外在住・永住していてもiDeCoに加入できることになります。
企業型確定拠出年金(企業型DC)・確定給付企業年金(DB)に加えてiDeCo加入はできるの?
結論からいうと、条件を満たしていれば企業型DCに加入している方もiDeCoに加入することが可能です。
以下にiDeCoと企業型DCの比較表を参考に記載しております。
iDeCoと企業型DCの比較
| iDeCo | 企業型DC | |
|---|---|---|
| 運営 | 国民年金基金連合会 | 実施企業 |
| 加入対象 | 原則65歳未満の従業員 | 対象となる従業員 |
| 掛金 | 本人負担 | 会社負担 |
| 掛金納入方法 | 本人口座から引き落とし | 会社より納付 |
| 運用商品 | 金融機関により異なる | 会社共通の商品ラインナップ |
| 手数料負担 | 本人負担 | 会社負担 |
| 税制メリット | 掛金は全額所得控除(所得税・住民税軽減) 運用収益は非課税 | 事業主掛金は所得とみなされない 運用収益は非課税 |
| 年末調整 | 必要 | 不要 |
iDeCoとマッチング拠出(企業型DC)との比較
さてマッチング拠出とは何か?で躓いている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
マッチング拠出
企業型DCで会社側の掛金に上乗せして、自身も掛金を拠出できる制度です。
マッチング拠出が可能な企業型DC加入者はマッチング拠出かiDeCoの加入かを選ぶことが可能です
| iDeCo | マッチング拠出 | |
|---|---|---|
| メリット | – 会社員は65歳到達まで加入可能(転職してもOK) 個人で商品ラインナップを選択可能 | 追加手数料無し 企業型DCの資産と合わせて運用 |
| デメリット | iDeCo手数料が掛かる iDeCo手続きは自分で実施 | 事業主掛金額を上回る掛金設定不可 企業型DCの商品ラインナップのみ 60歳前に会社を退職すると、他の制度へ資産を移動する必要あり |
iDeCoの掛金上限の変更予定
| 種類別 | 2022年9月まで | 2022年10月以降 | 2024年12月以降 |
|---|---|---|---|
| 企業型DCとDB | 1.2万円(※) | 月額2.75万円―各月の企業型DCの事業主掛金(月額1.2万円が上限) | 月額5.5万円―(各月の企業型DCの事業主掛金+DB 等の他制度掛金相当額)(月額2万円が上限) |
| 企業型DCのみ | 2万円(※) | 月額5.5万円―各月の企業型DCの事業主掛金(月額2万円が上限) | 月額5.5万円―各月の企業型DCの事業主掛金(月額2万円が上限) |
| DBのみ | 1.2万円 | 1.2万円 | 月額5.5万円―DB 等の他制度掛金相当額(月額2万円が上限 |
| 企業型DC・DB 共になし | 2.3万円 | 2.3万円 | 2.3万円 |
iDeCoとNISAの違いは?
iDeCo
老後資金を貯蓄運用しておくことが主目的になっていますので、貯蓄した資金は原則60歳以降に引き出しが可能
投資対象は投資信託、定期預金、保険商品であり、上場株等は対象外
NISA
投資運用が主目的なため、いつでも売却し引き出しが可能です
つみたて投資枠と成長投資枠の2つがあり、成長枠であれば上場株等への投資は可能
| iDeCo | NISA | |
|---|---|---|
| 目的 | 老後資金 | 広範囲な投資 |
| 対象年齢 | 原則20歳以上60歳未満 | 18歳以上 |
| 引き出し | 原則60歳以降 | いつでも可能 |
| 投資対象 | 投資信託、定期預金、保険商品 | つみたて投資枠 長期・積立・分散投資に適した一定の投資信託 成長投資枠 上場株式・投資信託等 |
| 運用上限額 | 1,800万円 | 年間144,000円~816,000円 |
| 手数料負担 | 本人負担 | 会社負担 |
| 税制メリット | 掛金は全額所得控除(所得税・住民税軽減) 運用収益は非課税 | 配当・運用収益は非課税 売却益非課税 |


コメント